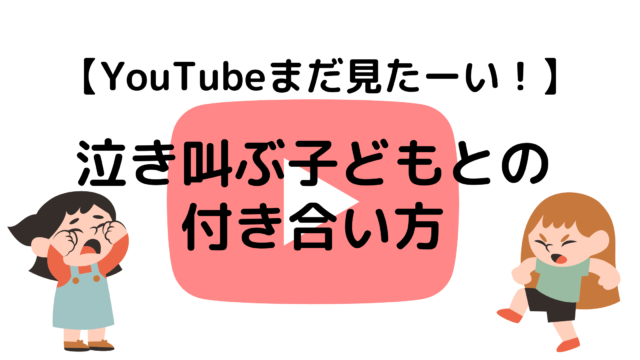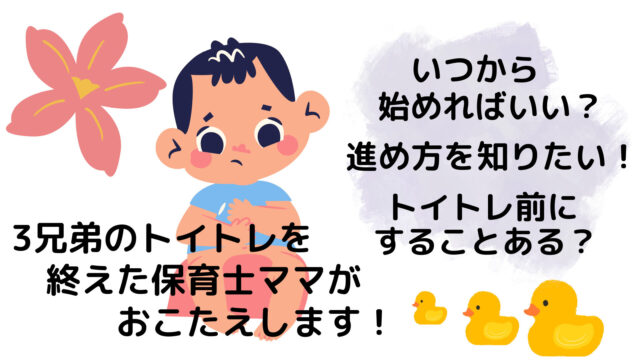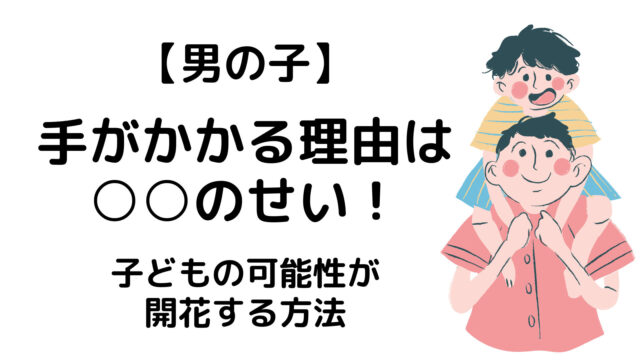子どもの成長は本当に早いもの。
2・3歳になると口も達者になってきます。
「ママ嫌い!パパがいい!」
このようなことも言うようになり、
嬉しいような悲しいような気持ちになりますよね。
子どもの成長過程において、「好き・嫌い」の自我が発達は自然なことです。
言葉の意味に一喜一憂してしまいがちですが、どんな言葉を言っていてもパパママはお子さんにとって世界で一番の存在です。
とはいえ、、
このような状況が長引くのは、パパママお互いに良くない影響が生まれてしまうのも事実です。
このような2・3歳のパパママさんに向けて、子どもに「やってはいけないこと」と「やるべきこと」についてお話しします。
\この記事のポイントを先取り/
【やってはいけないこと】
問い詰める
子どもの前でママの悪口を言う
甘やかす
めんどくさがる
【やるべきこと】
気持ちをアイメッセージで伝える
自分自身も振り返る
家庭のルールを親も守る
子どもの気持ちに寄りそう
子どもと過ごす時間を増やす
ぜひ最後までご覧くださいね!
もし「やるべきことだけ知りたいよ~」と言う方がいたらこちらからどうぞ!


2歳3歳「ママ嫌い!パパがいい!」この子どもにやってはいけないこと4つ

2・3歳の子供が、
「ママ嫌い!パパがいい!」と泣いたり拒否したり…
この姿は決して珍しいことではありません。
でも、、
この状況を悪化させてしまう親の行動があるのをご存じでしょうか。
以下の章では、
これだけ注意すれば大丈夫!子どもへやってはいけないこと3つを紹介します。
やってはいけない事① 問い詰める
1つめは子どもを問い詰めることです。
- なんでママが嫌いなの!?
- どうしてママを避けるの!?
- こんなに毎日一生懸命お世話してるのに…!
このように問い詰めることで、
子どもの心はママから遠ざかってしまいます。
「イヤ!」と言う子どもを目の前に、そう思う気持ちはとってもよくわかります。
感情的にならないためにもどうしたらよいでしょうか?
そんな時、マインドフルネスが役に立ちます。
最後の章で紹介していますので先に読みたい方はこちらからどうぞ!
やってはいけない事② 子どもの前で悪口を言う
やってはいけないこと2つめは、
パートナーへの悪口を言うことです。
- ママ怖いもんね~
- いつもうるさいもんね~
- ママが悪いよね~
パパから言われたら…腹立ちますねw
子どもの「ママ嫌い」を加速させてしまう原因となりますし、夫婦関係にもヒビが入ります。
極力、控えましょう。
もし言われた場合には「子どもがマネするし私も傷つくからやめてほしい」と伝えてみましょう。
やってはいけない事③ 甘やかす
やってはいけないこと3つめは「甘やかす」です。
言いなりになるような甘やかしはお互いのためになりません。
いけないことを「いけない」と教え伝えるのは大切な親の役目です。
こんな状況であっても、穏やかに・でも真剣に、伝えることは時に必要です。
私はこんな風に伝えていました。
「ママ嫌い」って言われたら悲しい気持ちになるの。
”今はパパがいいの、ごめんね”って言ってほしいな。
子どもが何かいけないことをした時ママが注意をし、
子どもがパパがいい!と甘えてきたとします。
前項でも触れましたが、ここでパパが「よしよしママ怖いね~」と甘やかしてしまってはNG。
ママを非難するような発言をしてしまうと、
子どもは「自分が正しい・パパは許してくれる・ママは間違い」という錯覚を起こしてしまいます。
- 社会や家庭のルール
- 人に迷惑をかけること
- 大きなケガにつながること
- 心身を傷つけること
- 不衛生なこと など
親としてルールを守る大切さを伝えていきましょう。
先に読みたい方はこちらからどうぞ!
やってはいけない事④ めんどくさがる
「ママ嫌い!パパがいい!」こんな状況は時間のない中少し(いやかなり)面倒な状況に感じることもあるかもしれません。
ですが、めんどくさがり何も対応しないのはお互いのためになりません。
例えば…
- 嫌われたくないから注意しない
- どうせ話を聞かないから注意しない
- 「○○してたよ」とパートナーに注意を押し付ける、逃げる
避けたくなる気持ちもわかります。
めんどうだな、と思う気持ちもわかります。
子育てってホント、根気も体力も忍耐も必要ですよね…w
2歳3歳「ママ嫌い!パパがいい!」この状況が続くと起こる良くない影響とは?
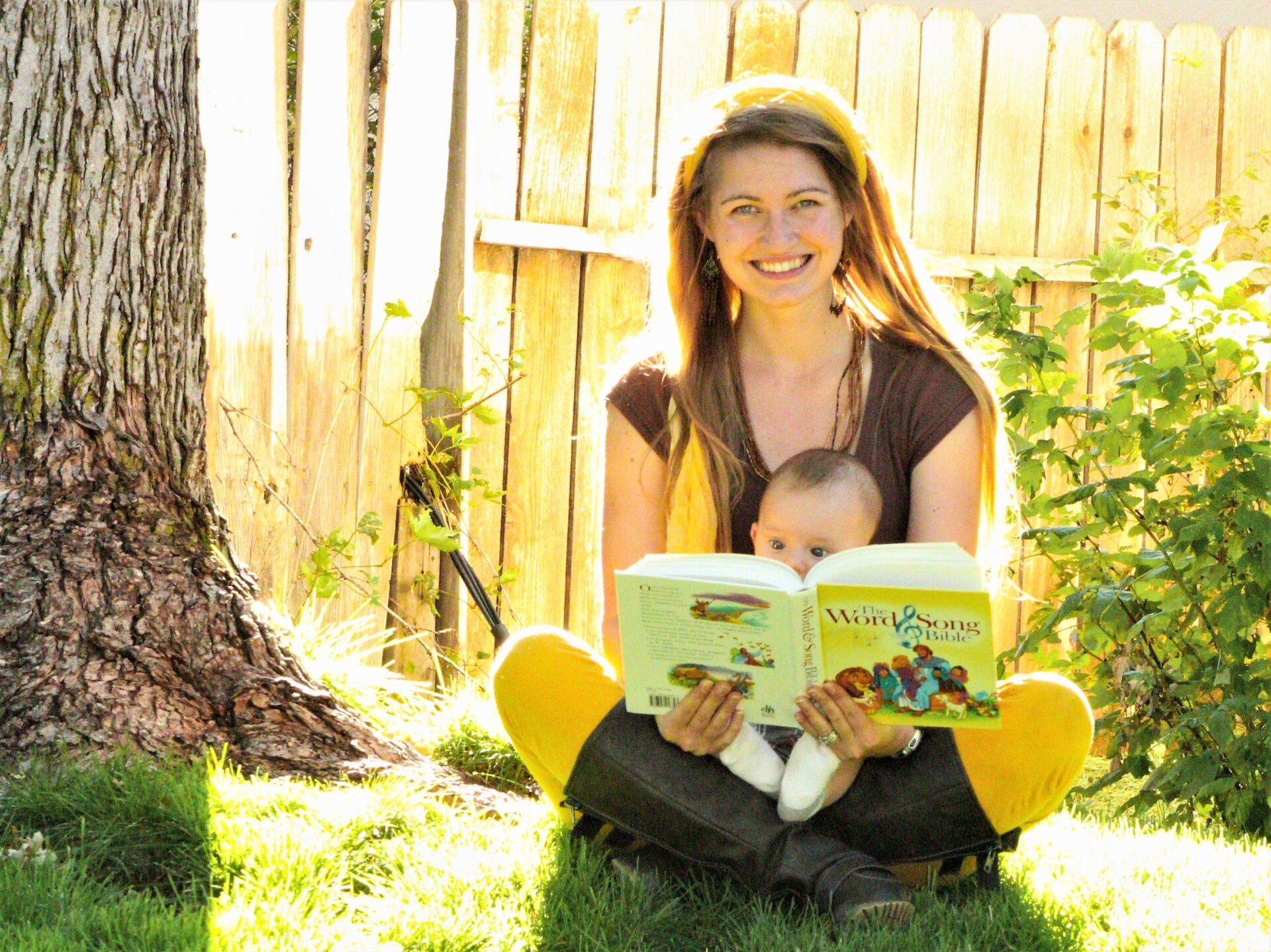
繰り返しになりますが2・3歳の子供が、
「ママ嫌い!パパがいい!」という状況はよくあることです。
ですが、
やってはいけない事をし続け「ママ嫌い!パパがいい!」この状況が続くと、
家族に良くない影響も少なからず起こってきます。
ここでは「ママ嫌い!パパがいい!」という状況が続くと起こる良くない影響を紹介していきます。
未然に防ぐためにも、知っておきましょう。
別に興味ないかな!と言う方は、次の「やるべきこと」や「子育てに役立つマインドフルネス」にとんでくださいね!
良くない影響① ママのいうことを聞かなくなる
やってはいけないことをし続け「ママ嫌い!パパがいい!」という状況が続くと、ママの言うことを聞かなくなることがあります。
その状況が続くと普段お世話をしているママの場合、生活しづらくなってしまうかも。
ママ嫌い!と言っていても、
子供はママのことが大好きです。
- ママも好きパパも好き
- ただ、パパの気分
- パパはいつもいないから特別感
- ママが嫌いなわけではなく
パパに甘えたい気分 など
子供の心はこのような場合が多いです。
その時その時で「ママ嫌い!パパがいい!」の理由が違うこともあります。
パパとママがそろう休日には、
パパの話はよく聞きママの話は全く聞かない、という場合もあるでしょう。
普段子どものお世話をしているママと子どもとのコミュニケーションが取りずらく生活しづらい状況になる場合があるので、注意が必要です。
関連記事がありますので紹介しておきますね!

良くない影響② ママが辛い
大好きなわが子に「嫌い」と拒否し続けられると…凹みますよね。
やってはいけないことを繰り返しこのような状況が続くと純粋にママが辛いです。
子育ての「よくあること」とはいえ、ママは毎日子どもと向き合い、向き合っているからこそ悩むし憤りを感じやすくなります。
ストレスや不安感が増すだけでなく、子育てに対してネガティブな感情を持つようになりかねません。
(私はなりかけてましたw)
私の関り方が悪いから…と自分自身を攻めてしまうことも。
これは、注意信号です。
子育てにおいてママの心の安定は最優先事項です。
後半のやるべきことや子育てに役立つマインドフルネスを参考に上手に乗り切っていきましょう。
良くない影響③ 夫婦仲が悪くなる
男性が育児に関わることが増えた今は、少ないかもしれません。
でも…ママを悪者にしたり責めることがあると夫婦仲が悪くなることがあります。
- 「ママ怖いね、やだねー」とママを悪者にする
- 「パパがいい」と言うのはママが悪いからと責める
- 「イヤ」と言われたパートナーの気持ちに気付かず放置
このような状況が続くと、ママのメンタルがやられてしまい夫婦仲が悪くなる可能性が高くなります。
関連記事がありますのでこちらも読んでみてくださいね!

2歳3歳「ママ嫌い!パパがいい!」この子どもにやるべきこと4つ!

2・3歳の子供の「ママ嫌い!パパがいい!」
このような状況を改善するためには、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか?
以下ではいよいよ、
この状況を心持ち楽に乗り越える「子どもにやるべきことを3つ」を紹介します。
やるべき事① ママの想いをパパがアイメッセージで伝える
まず1つめは、ママの想いをパパがI(アイ)メッセージで伝える方法です。
ママが直接「嫌い」と言われた悲しい気持ちを伝えるのも効果的です。
ですが、パパがいい!と言っている以上ママよりもパパの方が聞き入れてもらえるでしょう。
(伝えたその時反応がなくても、子供は心で聴いてしっかり覚えているものです)
ここでは「パパがママの想いを代弁する伝え方」を紹介します。
- 「ママが嫌い」なんてパパは悲しい
- ママは(子ども)が大好きなんだよ
- パパは(子ども)もママが好きになってくれたら嬉しいな
- ママの○○なところがパパは好きだよ
- ママは(子ども)のこととっても大事に思ってるんだよ など
このようにママの想いやパパの気持ちをアイ(I)メッセージで伝えます。
そうすることにより、子どもはパパの気持ちもママの気持ちも知ることができます。
また、ママのプラスなところに目を向け、子どもの気持ちに寄り添った話をしてあげるのも効果的です。
- ママが髪の毛を可愛くしてくれたね、嬉しいね
- ママは公園で一緒に遊んでくれて優しいね
- (子ども)が好きなハンバーグ作ってくれて嬉しいね
- ママがいつもお部屋をきれいにしてくれてありがたいね など
普段ママに感謝をあまり伝えられてない…!というパパは、子どもがくれた「パパがいい!」この機会をフル活用していきましょう!
言葉かけだけでなく、ママの好きなスイーツを用意したり・ねぎらいの言葉をかけてあげるのも効果的です。
ちょこっとだけ…自分自身も振り返ってみて
「ママ嫌い!パパがいい!」という姿は、多くの場合は成長の過程のひと時。
一過性のことが多いですが…
子どもの「困った行動」は、「寂しい気持ち」が表れている可能性があることも頭に入れておきましょう。
そのため、パパもママも子どもとの関わり方をちょこっと振り返ってみましょう。
- 子どもへ注意ばかり
- 子どもと過ごす時間がとても少ない
- 子どもと一緒にいても他のことを考えている
- パートナーに対し暴言や荒い態度で接している
このような場合は要注意です。
「寂しいよ…もっと僕(私)を見てほしい…」
このようなサインかもしれません。
それに…
子どもの姿は良くも悪くも、パパ・ママの心が現れます。
少し…疲れていませんか?
悩みごとを抱えていませんか?
子供は敏感に感じ取っています。
先ほども触れましたが、
子育てにはママの心の安定が最優先事項です。
子供のためにもまずはあなたが元気になってください。
やるべき事② 家庭のルールを夫婦で守る
夫婦内で家庭のルールが定まっていないと「ズレ」が生じます。
怒っているママが悪い・パパが正しいという構図になりがちです。
そんな状況…辛いですよね。
それを防ぐためにも、家庭のルールを共有していきましょう。
「パパはいいのにママはダメ」
このような状況は子どもを混乱させます。
小さいうちは子どもが混乱しないよう、同じルールで接してあげることが大切です。
…とはいえ、、
うちのように「夫婦が同じ方を完全に向く」というのが難しい夫婦もいるのも事実です。パパに口出すとキレてめんどくさくなるパターンでした。私は子どもの前でパパに口を出すのをやめました。小学校低学年ころから私は旦那の価値観と私の価値観の違いについて息子と娘に伝えています。「お父さんとお母さん違うんだもん…」こんなことを言われたこともありました。その度に謝り、繰り返し両方の気持ちや価値観を伝えていきました。子ども自身が選び「自分」を作っていけるよう「お父さんはこうなんだ、お母さんはそうなんだ、僕はどうしたいかな…」考えるきっかけになればいいなと思っています。
やるべき事③ 子どもの気持ちに寄りそう
やるべき事3つめは、嫌い・好きという気持ちに寄りそうです。
穏やかに子どもの姿を受け入れ・認めていきます。
- そっか~今はママは嫌なんだね
- そっか~今はパパの気分なんだね
- わかったよ~そんな時もあるよね
言葉で寄りそってあげてください。
ママが嫌いになったわけではなく、ただパパに甘えたいだけかもしれません。
パパブーム・パパ気分なだけかも。
でも…「嫌い!」と言われた方は傷ついてしまいますよね。
ママの気持ちを知る良い機会ととらえ「嫌い」と言われた気持ちを素直に伝えてあげる方法も効果的です。
そっか、ママ嫌なんだね。でも、嫌いって言われたら悲しいな…
「今はパパの気持ちだからごめんね」って言ってくれたら嬉しいな
子どもの気持ちに寄り添いながら、こちらの気持ちを伝えられる聞き入れやすくなります。
その時は聞き入れた様子がなくても、心にはママの言葉が積もっています。
繰り返し、伝えてあげることがお互いのためになります。
3歳だった娘は「ごめんね、いまはパパがいいの…」と伝えてくれました。
たどたどしいお喋りしかできなかったのに、です。
夫婦で顔を見合わせて驚いたのを覚えていますし「伝え続ければ子どもはわかってくれるんだな」と改めて感じました。
やるべき事④ 子どもと過ごす時間を増やす
働きながら子育てが「当たり前」になっている今。
とってもお忙しい毎日を送っている事と思います。
「子どもと過ごす時間を増やそう!」と言われても、困ってしまいますよね。
「パパがいい!ママ嫌い!」という姿は、先ほども紹介したようにコミにケーション不足からくる「寂しい」のサインかもしれません。
そこで下記では、効率的(と言っては語弊がありますが…)にパパ・ママの愛情を感じやすいタイミング・関わり方を紹介します。
ぜひ以下のタイミングにコミにケーションを取り、子どもの心を満たしてあげましょう。
子供の心を満たしやすいタイミング
- ご飯の時
- お風呂の時
- 寝る時
この3つは絶好のタイミングです。
とはいえ、
ここが一番忙しいタイミングなんだよな、、という方もいると思います。
わかりますw
でも…「寂しいのサイン」を見逃すと、後々お互いに苦しい状況に発展しかねません。
「できる限り」でかまいません。
私が心がけている「関わり方」を紹介します。
1つでも気になるものを試してみてください。
- ハグ
- 実況中継
- くすぐる
- 口角上げる
- 読み聞かせ
- 大好きと言う
- 頭や背中をなでなで
- 子どもへインタビュー など
子育てに役立つマインドフルネス

「ママ嫌い!パパがいい!」子どもを目の前に、どうしたら感情的にならずに穏やかに冷静に対応することができるでしょうか。
そこで役に立つのがマインドフルネスです。
>マインドフルネスとは?(準備中)
「ママ嫌い!パパがいい!」その状況になったら、、
ゆっくり呼吸して、自分の心の状態を観察してみましょう。
- イヤと言われて悲しいんだな
- 話を聞いてほしいんだな
- いつもお世話しているのに…
悔しいんだな - 旦那に嫉妬しているんだな… など
自分の心に気づくことができたら否定せず、そのまま受け入れます。
この間に少し、冷静になれると思います。
カッとなって行動することを防ぐことができ、自分の行動を選べます。
ゆっくり深く呼吸を続け、次は子どもへマインドフルになってみましょう。
子どもの今感じていることや、気持ちに寄り添ってみます。
- この子は今どんな気持ちなんだろう?
子どもの心に寄り添いながら観察・分析してみましょう。
- ママの気分じゃないんだな
- パパがイイだけかな?
- いつもいないパパがいいんだな
- そんな時もあるよね
そうして捉えなおし(リフレーミング)してみてください。
- 自己主張ができてる証拠
私と信頼関係ができてるんだな - パパとの関係ができている証拠
そう思うと少し、気持ちが楽になりませんか?
「そっかそっかママ嫌いか~。でもママは大好きだよ。ママがよくなったらいつでも待ってるよ~」
と、伝えられると子どもは安心できます。
「パパがいい!」と言いながらも、なんだかんだママが一番大好きですから。
2歳3歳「ママ嫌い!パパがいい!」この子どもにやってはいけない・やるべき事を徹底紹介! まとめ

この記事では、「ママ嫌い!パパがいい!」2・3歳のお子さんにやってはいけない事・やるべき事を紹介してきました。
成長の過程のほんの一時。落ち込む必要も責める必要も、全くありません。
でも…
もしかしたら「寂しいサイン」かも…ということも考えこの記事を参考にしてみてくださいね!
私・ゆでたまごはこのような想いをもって日々子どもと向き合っています。
- 子どもと子育てが好き
- なるべく叱らずにいたい
- 笑顔あふれる心地よい家庭にしたい
- ごきげんでいつでも頼れるお母さんでいたい
子どもと子育てに向き合って12年。
これまでに学び今もわが子へ実践している【ママのための心のセルフマインド術】をX(旧Twitter)やStandFMでお伝えしています。
ぜひフォローして『関わり方のコツ』や『マインドフル思考』を受け取ってくださいね。
読んでくださったあなたとの交流も楽しみにしています!
そして、家庭の笑顔が1つでも増えるきっかけになれば嬉しいです^^
最後に無料で聴ける私が好きなオーディブル本を紹介します。
子どもの発達に関する科学を、日々の生活に取り入れやすい形にして紹介してくれています。
不思議だった子どもの姿に「へ~そうなんだ!」と膝をうつ内容でした。
無料体験で聴いて、サクッと退会してもOK。
ぜひ活用してみてくださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました。



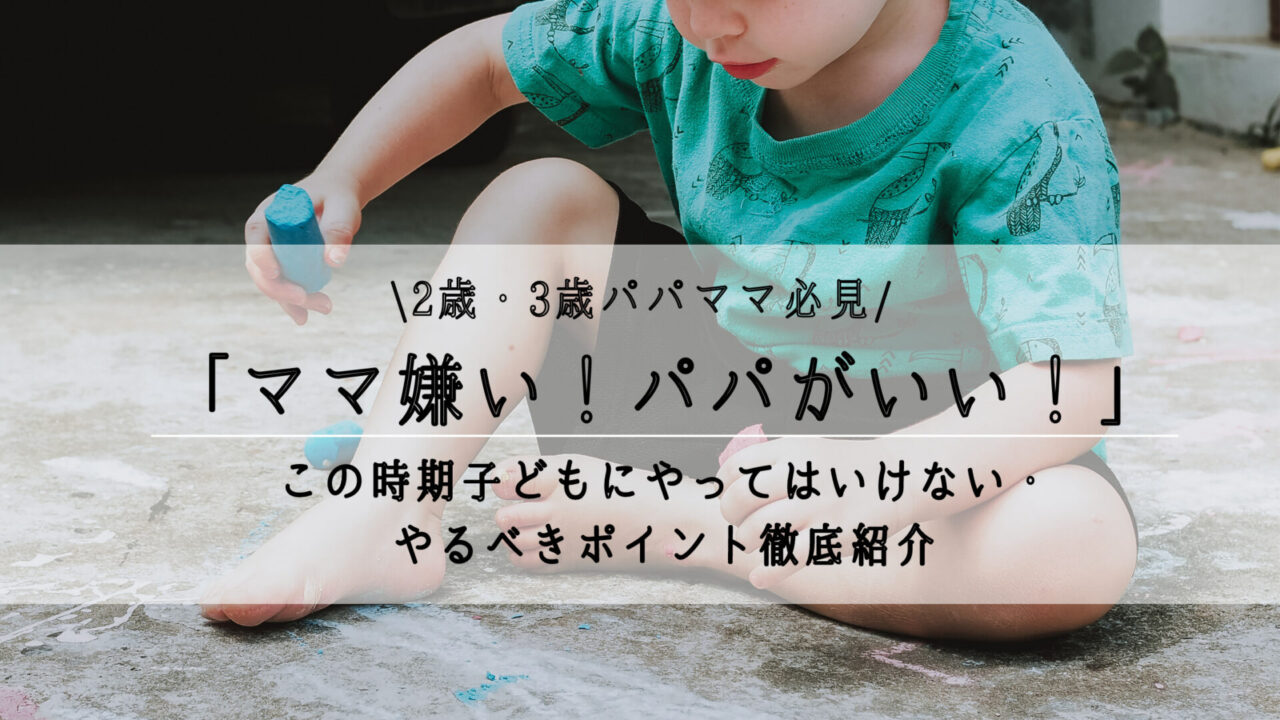



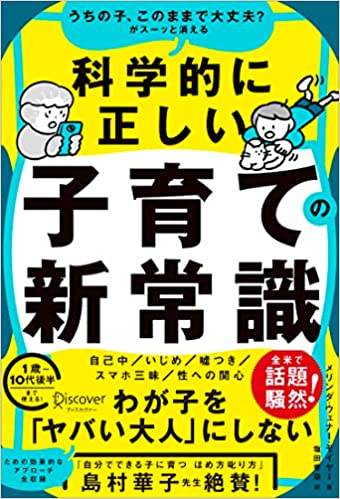 /1~10歳・子育てのヒントがわかる!\
/1~10歳・子育てのヒントがわかる!\